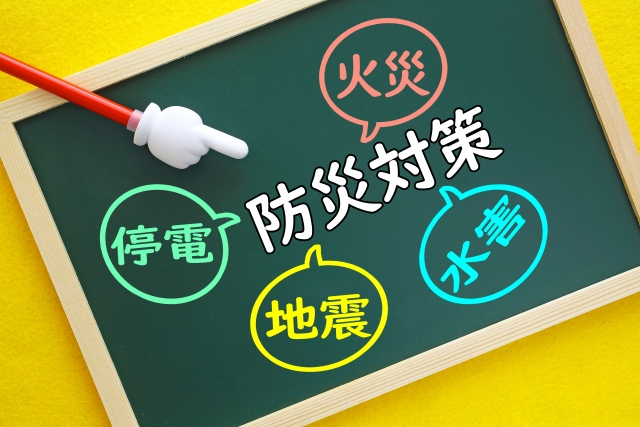「災害時の情報収集はスマホがあるから大丈夫!」と思っていませんか?
いつ起こるかわからない大規模な自然災害。
リアルタイムで情報を得るには本当にスマホでいいのでしょうか?
そこで今回は、災害時にラジオが必要な理由と選び方を紹介します。
災害時の情報収集に「ラジオ」が必要な3つの理由

災害時には避難所の確認や災害がどのように生活に影響しているかなどの情報収集は必須ですね。
災害時には停電や通信回線の遮断など予期しないアクシデントが発生します。
そのため、どのように情報を収集するかが問題となります。
結論から説明すると、おすすめなのが「ラジオ」を利用することです。
その理由は以下の3つあります。
1.停電でも情聞が得られる
停電が発生すると、スマホのバッテリーが充電できないそテレビやパソコンが使えない。
そんな影響がでます。
この場合、電池を使うラジオなら停電に関係なくリアルタイムで情報収集ができます。
また情報を発信する側のラジオ局では、停電でも非常用の電源があるので放送を続けることができます。
2.災害時はネットより電波が確実
インターネットは災害に強いことが知られています。
しかし、サーバーにアクセスが集中するとネットがダウンするリスクがあります。
非常時には相当の人がスマホで安否確認などで想定以上のアクセスが発生するリスクもあります。
そんな中でも光ファイバーや電線などの回線ではなく「電波」を受信するラジオは全く影響を受けません。
最新情報をいつでも、どこにいても受信できるメリットがラジオにはあります。
3.リアルタイムな情報が得られる
ラジオはリアルタイムで情報を聞くことができます。
ラジオ局では、現場の被害の状況や、避難所情報、医療関連情報、支援物資やボランティア関連などをリアルタイムで放送します。
テレビが見れなくても、スマホが通じなくても、ラジオなら最新の欲しい情報を得ることができます。
リスナーから寄せられる情報などは災害現場で役立つこともあります。
防災ラジオの選び方
ではどんなラジオが防災用に向いているのか選び方を紹介します。
電池式のラジオがオススメ
災害時に使うラジオは「乾電池式」がおすすめです。
乾電池さえ持っていれば、場所を選ばずに停電でも使えます。
もし充電するタイプ、家庭用100Vで動くラジオだと、100Vコンセントが必要になり停電では使えなくなります。
2019年の台風19号が千葉県を襲い大停電が発生した時に、乾電池式のラジオが役立ったことが知られています。
停電のためスマホで情報を得る人は、遠くの公民館まで充電に歩いていき数時間順番を待ちました。
シンプルなAM専用ラジオが省エネ!
ラジオはシンプルな構造でしかも省エネタイプがおすすめです。
大規模災害になると長期間にわたる停電に見舞われることも予想されます。
乾電池式のラジオは電池が長時間長持ちする省エネタイプが便利です。
災害時の情報は電波が遠くまで聞こえるAMラジオで十分。
FMの高音質でなくても、FMワイドバンドでテレビの音声が聞けなくても、実はAMだけで間に合った経験があります。
AM専用のラジオはFM受信回路が無いので省エネ。
ラジオに乾電池を入れるだけで、何カ月も長時間ずっと使えます。
ソーラー・手回し充電ラジオはサブ用で使う
災害時に手回し防災ラジオを使ったことがあります。
その手回し充電ラジオは防災用で10分間手回しして数分聞ける程度の発電量でした。
なので何度も何度も1日中手回し発電して疲れた経験があります。
また、ソーラー発電が付いたラジオは、太陽が当たらない屋内や夜間での充電、雨や曇りだと発電能力が極端に下がるので、充電まで相当時間がかかります。
その点、乾電池式ラジオは天候や場所の明暗の影響を受けないので災害時には役立ちます。
機能がシンプルなラジオは、とっても軽くコンパクトで邪魔にならないのがメリット。
なのでソーラー充電ラジオや手回し充電ラジオは、最終手段のサブ用として確保してもいいですね。
東日本大震災の教訓
一般社団法人 情報科学技術協会の「東日本大震災時にメディアが果たした役割(<特集>災害と情報)」2012年62巻9号 p. 378-384の中で次のようにラジオを評価しています。
東日本大震災では、ラジオの貢献度がネット系メディアをはるかに上回ったと報告しています。
震災当日から特番編成を立ち上げ,以後CMなしの24時間放送を数日間継続し,被災状況に加え,ライフライン情報,生活関連情報,安否情報,避難所情報などを放送した。また,被災地では津波からの避難時および直後の時期にラジオを筆頭にマスメディアが大きな存在感を示した。東京など周辺地域ではSNSやストリーミング・サイトなどネット系メディアの役割も注目されたが,被災3県についてはマスメディアの貢献度,評価は,ラジオを筆頭にネット系メディアのそれをはるかに上回っていたことが実証された。
引用:一般社団法人 情報科学技術協会
つまり、大規模災害時にはラジオの果たす役割が大きいです。
そのためラジオはネットを上回る機能を持つことが東日本大震災の経験から実証されました。
当時、よく売れたラジオとは?
震災でよく売れて品切れになったという有名なラジオがあります。
そのラジオは、なんと当時1,300円程度で買ったAM専用のラジオです。(写真)

東日本大震災の後、便利で価格が安く、よく聞こえることから品切れに!
ぼくは、それから数年待って買いました。
あれから10年になりますが、今でも毎日このラジオを聞いています。
小さくてAM専用ラジオですが、10年たっても壊れません。
伸ばすアンテナが無いので面倒なし。横長で自立して置けるのも便利。
驚くのは電池の持ちの良さです。
なんと単三乾電池2本で、1日に3~4時間聞いても3か月程度は楽に持ちます。
現在Amazonで調べたら、AMとFMの2バンドラジオより、AM専用ラジオは価格が2倍近くするのですね・・・
現在はぼくが買ったラジオのタイプはありませんが、新しいタイプが出ているようです。
2つのタイプをAmazonで紹介します。
AM専用ラジオ
AMとFMのラジオ
災害時に防災ラジオが必要な理由のまとめ
災害時の防災ラジオが必要な理由を紹介しました。
いつ来てもおかしくない大規模災害、巨大地震は温暖化での巨大は台風などは話題です。
災害時に効果を発揮するラジオは必須の防災グッズです。